高齢者のキャッシュレス決済利用率と導入のポイント
近年、60〜70代を中心とした高齢者層でもキャッシュレス決済の利用が広がりつつあります。しかし、小規模店舗や地域密着型の業種では「高齢者にはキャッシュレスが浸透していないのでは」と導入に慎重な声も少なくありません。実際には、クレジットカードやQRコード決済、電子マネーなどを利用する高齢者も増えており、決済手段の多様化が店舗運営のカギとなっています。
本記事では、高齢者のキャッシュレス決済利用率や傾向、導入時の課題と解決策、効果的な運用ポイントまでを詳しく解説します。高齢者が多い商圏でも安心してキャッシュレス導入を進めたい店舗オーナーの方は、ぜひ参考にしてください。
高齢者のキャッシュレス決済利用状況
キャッシュレス利用率の最新データ
近年の公的・民間調査を総合すると、60〜70代の高齢者においてもキャッシュレス決済の浸透は顕著です。2024年9月に実施された60・70代500人対象の意識調査では、「現金払いもあるがキャッシュレスが多い」が44%、「ほぼすべてキャッシュレス」が18%となり、合計62%が現金よりキャッシュレスを優先していることが示されました。
現金のみを使うと回答した人は7%にとどまり、高齢者層でもキャッシュレスが主流になりつつある姿が浮かび上がります。同時期に公表された経済産業省の統計でも、60代・70代全体のキャッシュレス利用率が約6割に達しており、年代差を大きく感じさせない水準になりました。
こうした結果は、決済事業者による大型ポイント還元や自治体発行のデジタル商品券といった政策・施策が高齢者にも波及し、現金中心だった支払い習慣が着実に変化していることを示唆しています。都市部と地方では依然としてキャッシュレスの普及率に差があるとされており、地方では現金利用が依然として優位な地域もあります。
一方で、クレジットカードや一部のQRコード決済などは全国的に普及が進みつつあり、地域間の格差は徐々に縮小する傾向も見られます。高齢者層を含め、全国的にキャッシュレス利用の裾野が広がり始めている点は注目されます。
支払い手段別の利用傾向
前述の500人調査によれば、高齢者が最も頻繁に利用しているキャッシュレス手段はクレジットカードで57%でした。次いでQRコード決済が26%、交通系を中心とするIC型電子マネーが13%という順序になっています。別の全国1,130人を対象とした2024年5月の調査では、QRコード決済の利用率は60代で約50%、70代で約30%に達しており、前年から60代で7〜8ポイント伸びるなど拡大が続いています。
IC型電子マネーは「交通機関利用と紐づくので時々使う」とする回答が60代前半で多く、都市部を中心に根強い支持があります。これらの数字から読み取れるのは、クレジットカードを軸にQRコード決済と主要IC電子マネーを組み合わせる三方式併用が、高齢者市場でも標準的になりつつあるという点です。実店舗がシニア顧客の利便性を高めるには、この三方式を網羅する決済環境を整えることが欠かせません。
スマホ所持率とデジタルリテラシー
キャッシュレス利用の前提となるスマートフォンの普及も進んでいます。MMD研究所が2024年12月に60〜79歳1万人を対象に行った調査では、同世代のスマホ保有率が約90%と報告され、2014年頃の20%台からおよそ4倍に拡大しました。ただし「契約や設定で家族などのサポートを受けた経験がある」人は半数を超え、日常利用でも約4割が何らかの支援を頼りにしている実態も判明しています。
一方で「ポイントアプリやメッセージアプリを自分一人で使いこなしたい」と回答した人が25%超おり、正しいフォローがあれば自立的なデジタル活用意欲は高いことがわかります。レジでスタッフがアプリ選択やQR読み取りを声掛けで補助するだけで決済完了までの時間が短縮でき、高齢者でもストレスなくQR決済を取り入れられる素地は十分に整っています。
高齢者がキャッシュレス決済を使わない理由・課題
店舗側の導入ハードル
小規模店舗では決済端末の初期費用や加盟店手数料が心理的負担になりがちです。とりわけシニア客が多い業態では「導入しても使われないのでは」という懸念から現金専用レジのままというケースも少なくありません。しかし実際には60〜70代の約6割がキャッシュレス主体で支払っており、導入の遅れは売上機会を逃すリスクにつながります。
近年は初期費用0円や売上連動型手数料プランを打ち出す事業者が増え、端末自体もキャンペーンで無償提供されることが多いなど、コスト面の障壁は確実に低下しています。導入可否を判断するときは「費用がかさむ」という先入観だけでなく、実際のコストダウン策と利用実態データを冷静に比較することが重要です。
高齢者の操作性・心理的障壁
高齢者がキャッシュレスを敬遠する主な理由は、「現金の方が簡単・便利だから」や「セキュリティへの不安」、「操作が難しそう」といった点です。また、「リアルにお金管理できない不安」や「使い過ぎへの不安」なども挙げられていますスマホ保有率が9割になっても、複雑な画面遷移や小さな文字はハードルであり、約4割が日常的に家族の助けを借りています。
店舗スタッフが「アプリを開く」「QRを読み取る」「金額を確認する」という手順をその都度声掛けするだけで決済は円滑に進み、待ち列のストレスも軽減します。さらにIC電子マネーやクレジットカードのタッチ決済を併用すれば、画面操作に慣れていない高齢者でもワンタッチで支払えるため、心理的障壁を大きく引き下げることができます。
システム・手数料の複雑さ
利用者側からは「ポイント還元率やチャージ方式がサービスごとに違い、結局どれが得か分からない」という声が根強く残っています。店舗側も手数料率やキャンペーン条件の変更を追い切れず、情報更新の負担を感じやすいのが実情です。
しかし近年は自治体や決済事業者が公式LINE、メールマガジンで最新情報を自動配信し、加盟店向けに比較表を提供するなど支援策を拡充しています。こうしたツールを導入すれば、複数サービスを扱っても情報更新の負担を最小限に抑えられ、シニア顧客にも分かりやすい還元説明が可能になります。
店舗が知っておくべき高齢者向けキャッシュレス導入ポイント
決済端末の種類と対応手段
現在主流のモバイル型マルチ決済端末は、クレジットカード・ICカード・QRコード決済を一台で処理でき、BluetoothでPOSレジと連携する機能も備えています。タブレット操作が苦手なスタッフがいる場合は物理キー付き据え置き端末を併設すると「昔ながらのレジに近い」操作感を提供でき、高齢者へも視覚的に安心感を与えられます。
暗証番号入力時に音声ガイダンスが流れ、大きな数字表示を備えたモデルを選べば、入力ミスを防ぎスタッフのサポート負荷も軽減されます。
初期費用・手数料の比較
キャッシュレス決済の導入にあたっては、初期費用や手数料体系を事前に把握することが重要です。多くの決済サービスでは、端末費用や月額利用料が無料、または一定条件下で無償となるプランが提供されています。手数料については、決済手段や契約内容によって異なりますが、売上に対する一定割合が課される従量課金制が主流です。
入金タイミングもサービスによって異なり、早ければ翌営業日から、一定の締め日に応じて月1回程度の入金となる場合もあります。自店の売上規模や業種に応じて、コストと入金サイクルのバランスを見ながら最適なサービスを選ぶことが大切です。
スタッフ教育とサポート体制
高齢者が決済で戸惑った際に頼りにするのは店舗スタッフです。新端末導入時は詳細な操作マニュアルよりも「声掛けフロー」を重点的に訓練し、決済失敗時の取消・現金受け直し手順を共有するとレジ停滞を防げます。また、サポート窓口の電話番号やチャット問い合わせ先をレジ横に掲示し、営業時間内に迅速な相談ができる体制を整えておくことで、スタッフの心理的負担が大幅に軽減されます。
高齢者へのキャッシュレス利用促進施策
操作サポート・説明会の実施方法
店舗のアイドルタイムを活用し、10〜15分のミニ講習を月1回程度開催すると、高齢者でも気軽に参加できます。実機を用いて支払い体験をしてもらい、終了後にワンドリンク無料券などの特典を渡すと参加率が一段と高まります。家族同伴を歓迎するとデジタルに詳しい子世代が自然にフォロー役となり、店舗側のサポート負荷も抑えられます。
ポイント還元・キャンペーン活用
高齢者層は「いつもの店で確実に得をする」仕組みに敏感です。決済事業者の大型還元キャンペーンと、店舗独自のスタンプカードやシニアデーを併用し「二重取り」を訴求すると、初回利用後のリピート率が向上します。自治体が発行するプレミアム付きデジタル商品券がある地域では、講習会とアプリ登録サポートを同時に行うことで利用者が一気に広がります。
分かりやすい案内・POP設置
レジ前には「手順を3行に絞った大型POP」を設置し、フォント24pt以上・高コントラスト配色とすることで視認性を高めます。QR決済なら「アプリを開く→店舗QRを読み取る→金額を入力して提示」、クレジットカードなら「カードを挿す→暗証番号入力→完了」という3ステップを図示すれば、会話が聞こえにくい高齢者にも直感的に伝わります。
おすすめキャッシュレス端末ブランド3選
「すぐに資金を受け取りたい」「決済手段の幅を広げたい」「訪日外国人に対応したい」など、店舗によって導入時に重視したいポイントはさまざまです。
本サイトでは、よくある重視ポイントである「入金サイクル」「決済手段の多さ」「インバウンド機能」に注目し、3つのキャッシュレス端末ブランドを厳選してご紹介しています。自店舗に適した端末選びの参考にぜひご活用ください。
まとめ
60〜70代の6割超がキャッシュレスを主要決済手段としており、スマートフォン保有率も約90%に達しました。クレジットカードに加え、QRコード決済と交通系IC電子マネーを組み合わせた三方式併用がシニア層でも定着しつつあります。端末費用無償化や売上連動型手数料プランの普及、即日入金オプションの拡大により、小規模店舗の導入コストとキャッシュフロー不安は大幅に軽減されました。
スタッフの声掛けサポートと視認性の高い案内POPを組み合わせれば、高齢者の心理的障壁を下げつつ会計効率化と新規集客を同時に実現できます。現金中心の高齢者顧客が多いと感じている店舗こそ、今こそキャッシュレス導入を前向きに検討する好機です。
キャッシュレスを導入するのであれば、店舗の状況に合ったキャッシュレス決済端末を選びましょう。TOPページでは、「入金サイクル重視」「豊富な決済手段」「インバウンド対策機能」という3つの重視したいサービス別にキャッシュレス決済端末を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
キャッシュレス決済端末を選ぶ際に重視されやすいサービス別で、おすすめの決済端末を紹介しています。
最短翌営業日に入金可能な
(Square株式会社)

(https://squareup.com/jp/ja)
- スタートしたばかりで客入りが安定していない飲食・小売店
- 保険適用分の入金タイミングにより繁忙期の運転資金に悩む接骨院・鍼灸院
入金サイクルは最短翌営業日。月2回支払いのキャッシュレス決済サービスが多い中、売上がすぐに手元に入ることが魅力。
迅速な仕入れが必要なイベント出店時でも、仕入れ用の資金を確保しながら運営が可能。
77種の決済が可能な
(株式会社リクルート)

(https://airregi.jp/payment/)
- 地元民の来店が多い地方都市にある個人経営のコンビニエンスストア
- 幅広い年代の客層が行きかう商店街に店を構える個店
77種の決済種類に対応。特定地域で展開しているアプリやQRコードなどにも対応しており、地域活性化や集客を支援する効果も期待できる。
地方銀行が提供する決済にも対応し、銀行とのつながりが強い高齢者への強みも発揮。
19種の通貨で決済が可能な
(三井住友カード株式会社)
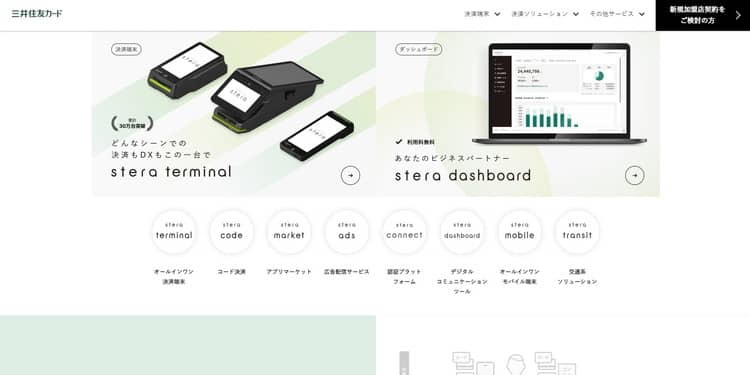
(https://www.smbc-card.com/kamei/stera/index.jsp)
- 海外旅行客が多く訪れる観光地の宿泊施設や土産物店
- 訪日外国人が多く来店する都市部のドラッグストアや家電量販店
米ドルを始めとした19種類の通貨で決済が可能なため訪日外国人へのサービス向上が可能。
また、免税処理をパスポートの読み取りと商品情報などの入力のみで行え、お客様とスタッフ双方の手間が省ける。

